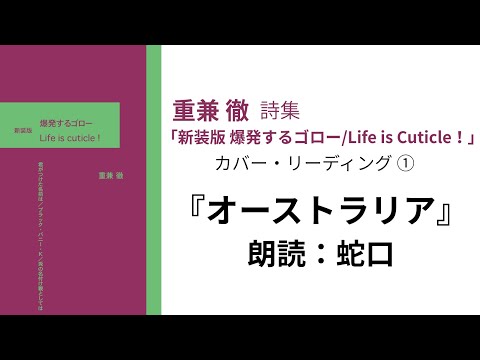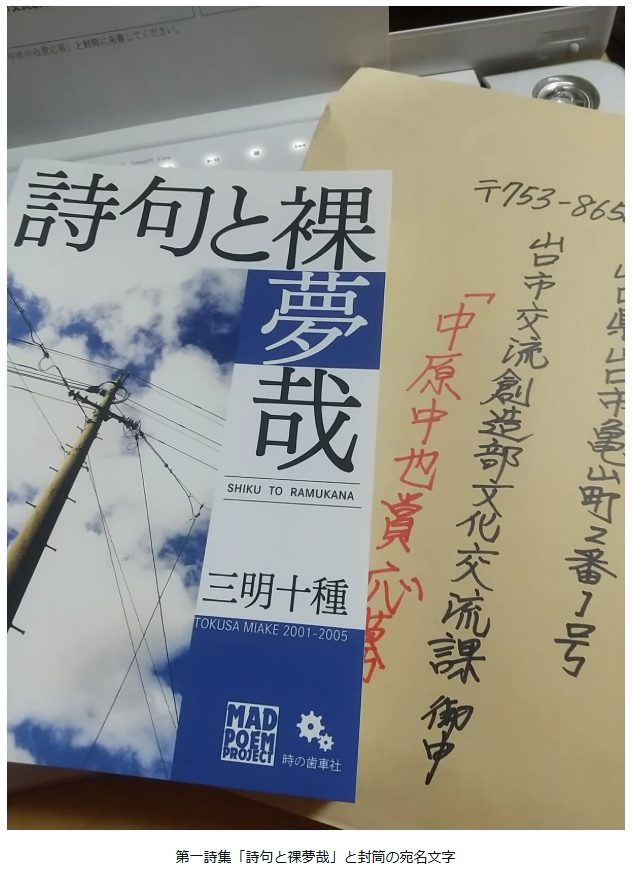「バニラ水滸伝」西村太一
もうすぐ昼が炊けるけど、その前に何か軽く食べたいな。お財布スカスカだけど、えーっと、200円と幾らかはあるな。バニラアイスで良いんだけど、出来たらジャンボフランク2本腹ごなしに食べたいな。無計画にお財布からはたいちゃうから、バニラかな。エレベーターの中でお財布の中見て、と。アイス店内で。レジを打ってもらいました。椅子に座っていつも通りのバニラアイス。先日どーのこーのと頭の中で喧嘩になっちゃったダンディなオジサマ辺りにアイスと言えばバニラですよね〜、なんてそろそろいつも通りのお買い物のお時間かな?いつも大体時間が一緒なんだけど。あたまが栄養スカスカはいっぱいになった。帰って卵かけご飯だ。店を出てタバコを吸っていたら、あら。来たんだ。水滸伝によると、これから108名の猛者がお店に向かわれる...